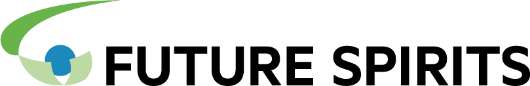はじめに
ここ数年、「AIが仕事を奪う」「AIで何でもできる」——そんな言葉をよく聞くようになりました。
でも、実際の現場では「(生成)AIって、どう使えばいいの?」という声のほうがずっと多い気がします。
私自身はというと、仕事のかなりの部分を生成AI(主にChatGPT)に肩代わりしてもらっています。
誤解を恐れずに言えば、すでに私の業務の何割かはAIがこなしています。
ただし、私はAIを“万能の神様”だとはまったく思っていません。
むしろ——優秀な右腕だと感じています。
今日はそんな私の生成AIとの向き合い方についてお話してみます。
生成AIは神様ではなく、優秀な右腕である
エンジニア界隈でよく聞くのが、
「生成AIは嘘をつくから使えない」
という声です。
確かに、生成AIは“ハルシネーション”と呼ばれる誤情報を、もっともらしく語ることがあります。
これが原因で失敗するケースも実際にあります。
ただ私はこう思っています。
「人間より間違いを言うことは少ないのではないか?」
ハルシネーションの原因はいくつかありますが、大きいのはプロンプト(指示)の精度です。
質問が曖昧なら、答えも曖昧になる。これはAIに限らず、人間相手でも同じです。
AIを“神様”として信じすぎると、間違いが出たときに「やっぱり使えない」と思いがちです。
でも、“右腕”として見るとどうでしょう。
多少のミスはあっても、疲れ知らずで、24時間いつでも相談できる頼もしいパートナーになります。
ある意味、AIは「疲れない右腕」です。
そう考えると、AIに対する見方も、付き合い方も変わってくるのではないでしょうか。
「どう使えばいいか分からない」時の最初の一歩
生成AIを仕事に取り入れていこうという話をすると、よくこんな話があがります。
「便利そうだけど、どう活用したらいいか分からない」
これは、ChatGPTなどのインターフェースが“チャット”であることも一因だと思います。
入力欄に何を書けば良いか分からず、最初の一歩で止まってしまう。
そんな場合、私の答えはシンプルです。
とりあえず、雑でもいいから投げてみる。
「習うより慣れろ」——完璧なプロンプトを考えるより、まずは自分の言葉で雑でも良いので投げてみることが大事だと思います。
優秀な右腕なので、こちらの曖昧な意図もかなり汲み取ってくれます。
むしろ、同じ内容を人に伝えるより、理解してくれることが多いと感じることもあります。
何度か投げているうちに、「こう聞くと精度が上がる」「こう聞くとハルシネーションが出やすい」が見えてきます。
ある意味、人とのコミュニケーションを学んでいくようなものです。
雑談を重ねるうちに相手の癖が分かるように、AIとの対話も積み重ねが重要だと思います。
私の活用事例
ここからは、私が実際に生成AIをどう使っているかを簡単に紹介します。
奇をてらった使い方はしていません。むしろ“普通の業務に地味に効く”使い方です。
調べもの
一般的にはこれが一番多い使い方だと思います。
昔はGoogle検索が当たり前でしたが、今はまずChatGPTに聞くことが多いです。
1~2年前のChatGPTでは、RAGデータの限界で古い情報や誤情報が多くありました。
しかし最近では、ChatGPT自体がWeb検索を併用するようになり、精度が格段に上がりました。
たとえば、1〜2年前ChatGPTに、
「大阪駅周辺で魚の美味しいお店を教えて」
と聞くと、
大阪駅前第3ビルの25階にある〇民がお勧め
と、このあたりに詳しい方であれば、実在しないことが一瞬で分かるような架空のお店が紹介されたものです(笑)
でも今では、同様の質問をすると、その場でWeb検索した上で、実在のお店を色んな視点で紹介してくれます。
壁打ち相手として
これも一般的によくある使い方だと思います。
ChatGPTなどの生成AIは話を要約することに長けているので、自分の考えをツラツラと書いて、それを要約してもらったり、アドバイスをもらったりすることがあります。
もちろん、人間相手の方が良い場面もあるので、そのあたりは使い分けかと思います。
資料作成の下ごしらえ
パワポなどの資料作成であったり、資料の叩き台を作ってもらうことが多いです。
これが結構便利で、何の資料をどんな風に作りたいかを伝える(プロンプト)ことで、骨子をまとめてくれたり、最近ではパワポファイルの作成までを肩代わりしてくれます。
ただ、ChatGPTは現時点ではパワポ資料の作成は得意ではないので、GenSparkなど別の生成AIを利用することがあります。
ちなみに、以前にGenSparkに当社の会社概要資料をパワポで作ってみてもらったんですが、プロンプトに当社のHPのURLを書いて、それを元に「会社概要資料を作成して」と指示するだけで、ほぼそのまま利用可能なレベルの資料がものの30秒程で生成することができました。
実際には一部おかしな表現などもあり、そのまま利用することは出来ませんでしたが、叩き台としては十分なクオリティで、ほんの少し手を入れてやるだけで十分利用できるレベルになりました。
業務ツールの自動生成
個人的にはこれが最も多い用途です。
ChatGPTに簡単な要件を伝えて、PythonやShellでミニツールを作らせています。
たとえば、
・エクセルのバッチ処理ツール
・サーバのログ解析ツール
・サーバ監視レポート作成ツール
・議事録作成ツール
など、あると便利だけど、商用製品を入れる程のボリュームではない。といった時にChatGPTで簡単なツールを作ったりします。
ちなみに、私は多少なりコードは読めますが、プログラマー経験はないので、自分でゼロベースからコードを書いてツールを作ることは得意ではないです。
そんな私でも、プロンプトで指示を出すだけで、それなりにリッチなツールを作成することができています。
ただ、この使い方は、前提として多少なりコードが読めたり、プログラムの基本的なことが分かっていないと難しいかもしれないので、「誰でも簡単」とまでは言えないかもしれません。
また、私は元々がサーバエンジニアで、作成したツールを動かす環境を用意することは得意なので、活用し易いといった点があるかと思います。
まとめ
今回は技術的な検証とかではなく、私自身が生成AIとどう向き合っているのか、どんな風に活用しているのかをまとめてみました。
生成AIのみならず、AI領域の進化は日進月歩で非常に早く、今日できなかったことが明日にはできるようになっていたりします。
そんな中で、特にエンジニア領域においては、生成AIを如何にうまく活用するのかが、今後のエンジニアに求められるスキルの一つになるかと思います。
エンジニア界隈では、「AIに仕事を奪われる」なんて話をよく耳にしますが、遅かれ早かれ今のエンジニアリング仕事の大半はAIに取って代わられるようになると思います。
それをネガティブに捉えるか、ポジティブに捉えるかは人それぞれだとは思いますが、個人的にはポジティブに捉えており、今の仕事をAIをやってくれるのであれば、その空いたリソースを使ってAIではまだ出来ない新たな領域にチャレンジしていえればと思っています。
今のところAIは1⇒100は非常に得意ですが、その特性上0⇒1は得意ではないため、そこは引き続き人間が牽引していく領域だと思っているので、AIでできることはAIに任せて、人間にしかできないことをやっていきたいと考えています。
追伸
この記事は、私が下書きを書いたあとに、ChatGPTに「もうちょっとイイ感じに直して」とお願いして整えてもらいました。
まさに、私の”右腕”として働いてもらっています(笑)