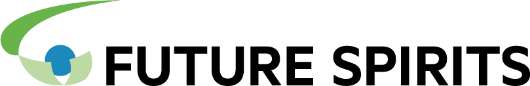◆
テストに関連する作業を行う際、対象がどの様な目的と機能を備えているかを知っている事は大事です。テスト仕様書を作るとしてもテストを実施するにしても、それらを知らなければ目的を達成する事は出来ません。テスト対象がどの様な物であるかは基本的に依頼主から説明される事が殆どですが、稀に唐突に動作の確認を依頼される場合があります。その様な時に確認すべきものが仕様書です。
仕様書はテスト仕様書ではなく、機能仕様書や画面仕様書の方です。これを見る事でテスト対象がどの様なものであるかと知る事が出来ます。それぞれの仕様書を繋ぎ合わせれば、何となくであってもどの様な機能があり、どの様な目的に合わせて作られた物なのか分かります。在庫管理システムなのか、ユーザーページなのか等々……大体の事は書いてある訳です。
過去に唐突に依頼された物で「動作しているか見てほしい」と言うものがあり、テスト仕様書も無く取り合えず出来ていた実物の方を触る事になりました。テスト実施する側とすると「説明が無くとも、動かせる対象があればある程度何とかなる」と言う気持ちはありますが、やはり各機能等の仕様は知っておきたいのが正直な所です。各入力欄に入力制限はあるのか、何処の誰を対象とした物なのかを知らずに実施する事も出来ますが、確認した結果が正しい物であるかの判断が出来ませんからね。そして、ある程度動かしてみた所で段々と本当に意図した動きなのか疑問が出てくる挙動にでくわしました。
そこで機能仕様書等は何処にあるかの確認を取り、仕様書に記載されている内容と画面の表示や各主動作を突き合わせて、想定された動作であるかの判断をしていく事になりました。その当時は仕様書の更新もされていなかった事もあり、全てが正確と言う訳ではありませんでしたが判断材料としては有効でした。エラーメッセージの内容や表示タイミング、ボタン押下から表示までのおおよその時間等を知る事が出来れば、現在触っているテスト対象の動作が求められている基準なのか分かります。これらは仕様書を確認しなければ、テスト対象を動かせていても分からない部分になります。
当時の最終的な結果としては、「一応期待した通りには動いていますが、仕様書に記載されている基準には届いていない」と言う形になり全般的な見直しが行われる事になりました。
本格的な製品テストに入る前に、「ひとまずの動作確認」と言うざっくりとしたものは、詳細を知らなくてもやる事は出来ます。ただやはり、最初に述べた様に仕様書を確認しその内容を知っておく事は非常に重要です。「説明が無くとも、動かせる対象があればある程度何とかなる」と言うふんわりとした感覚から、「仕様書に記載されている内容と異なる気がする」と明確な意識の違いと持って取り組む事が出来ます。
◆
何をするにしても仕様書と言うのは重要です。何の説明もなくテスト依頼される事は非常に稀な事とは言え、決して無いと言う事はありません。そういう時、取り敢えず仕様書を確認する事で対象の理解を深める事が可能で、テスト実施の意味合いも大きく変わってきます。「取り合えず動かして確認する」か「ある程度の目的と内容を理解した上で確認する」では、結果の信頼性や不具合についての詳細等について説得力が付いてきます。過去の話はある意味で極端な話ではありますが、例え更新されていない古い仕様書であったとしても、テストに関連した仕様書を読む事はとても大事な事です。テストを実施する前やちょっとした時間に、仕様書を読んでおくと実際の作業に入る時にとても役立つと言う話でした。